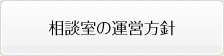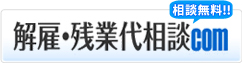- 過労死・過労自殺・労災の相談室|トップ
- 弁護士が担当した事件の紹介
- 精神障害による自殺未遂の労災事件
精神障害による自殺未遂の労災事件
平成24年7月5日 大阪高等裁判所判決
第1 事案の経過・概要
浄化槽の保守点検業務に従事する労働者が突然の懲戒を突きつけられての退職勧奨後の数日後に自殺を図ったところ(平成15年6月)、視力喪失等の重い障害を残して労働能力を喪失した事案である。
労災申請するとともに民事訴訟(損害賠償)を並行して行ったが、民事訴訟の一審、控訴審、最高裁とも敗訴が続いた。
一方の労災手続きについても負け続け、行政訴訟の一審である平成23年10月17日大阪地裁第5民事部における裁判でも敗訴し、今回の控訴審となった。
民事訴訟の高裁判決では労基署への調査嘱託によって退職勧奨直後に被災者が労基署に相談していた記録が開示されたことによって、民事の和歌山地裁の不当な事実認定(退職勧奨すらないというもの)を打ち崩すことができ、民事の大阪高裁判決において被災者が懲戒規定を突きつけられての退職勧奨(実質解雇)であることの事実認定までは獲得できた。しかし、後一歩のところで会社の責任までは認められなかった(予見可能性なし)。
並行して行われた労災の行政における不服申立手続き(再審査請求)における労働保険審査会では退職勧奨であることを前提に判断されたが、精神障害発症(急性ストレス反応)を認めつつも、「退職勧奨」の平均的な心理的負荷「Ⅲ」(人生の中で希に経験することもある強いストレス))で通常の流れで行くと業務起因性が肯定されるはずであった。ところが、結論が先にありきで業務外の原処分を維持するためとしか思えないが、退職勧奨直後に被災者が社長に対して居直った態度を取っていた、沈んだ様子を見せていなかったことなどから、退職勧奨によって受けた心理的負荷は「相当程度過重であったとは認められない」として、業務起因性を否定した。
第2 争点
行政訴訟における争点は概ね下記の3点であった。
(1) 被災者の発症した精神障害の有無
(2) アルコール依存症か否か、
アルコール依存症に基づく2次性うつ病などによる自殺に及んだのか
(3) 解雇の心理的負荷の程度
第3 弁護団の方針
(1) 民事訴訟と行政訴訟とは判断枠組みが異なる
民事訴訟については最高裁において敗訴が確定してしまっていたが、会社を相手とする損害賠償についての民事訴訟で負けたとしても労災の枠組みはそれとは異なる。したがって、民事訴訟において敗訴が確定していたとしても、行政訴訟では十分勝機があると信じていた。波多野が担当した国立循環器病センター事件(一審・控訴審とも勝訴・看護師の過労死の公務災害・大阪地裁平成20年1月16日判決・労働判例958号21頁大阪高裁平成20年10月30日判決・労働判例977号42頁労働判例977号42頁)においても、民事賠償の訴訟において最高裁まで行って敗訴が確定していたが、行政訴訟では勝訴できた。
(2) 主張立証方針は単純明快(これまでの手続きで獲得した事実認定・判断を基礎に)
民事訴訟で敗訴したとはいえ、民事賠償の大阪高裁判決は、「自宅謹慎中の従業員を社用車に乗せた話をしていたというだけでは、直ちに控訴人の従業員としての適格性に疑問を生じさせたり、労使関係における信頼関係を破壊するとはいえないことは明らかであって、専ら上記のような理由で行われた本件解雇に正当な理由があったとは認めらない」として、不当解雇であるとの判断がなされていた。
弁護団としてはこの大阪高裁判決の事実認定・判断を足がかりに「退職強要(本件解雇)」(心理的負荷Ⅲ)→精神障害発症(適応障害等)→自殺企図という因果の流れを具体的に立証することに成功すれば、勝てるはずとの見通しを立てた。
既に医学意見書は複数提出していたが、さらに退職強要後に適応障害を発症したことに関する原告側の医学意見書を提出できた。
第4 大阪地裁平成23年10月17日判決・労災1審の敗訴判決の概要
(1) 適応障害発症否定
大阪地裁判決は、本件解雇後、被災者が社長に「辞めてやるわい」と言って退社していること、労基署へ相談に出向いていること、再就職先について相談しているなど退職に向けて合理的な行動をしているとして適応障害発症を否定した。
(2) 本件解雇の負荷の評価の誤り
大阪地裁判決は、不当な労務管理による負荷があったとまでは認めることはできないとしつつ、本件解雇について「一定程度の心理的負荷」があったことは認めつつも、被災者が社長に対して、「辞めてやるわい」と反論したり、異議を述べていない、再就職の行動をしていたなどとして、「解雇によって受けた心理的負荷は、その程度が強いものであったとまでは認められない」とした。
大阪地裁のかかる判断は、最低基準であるはずの行政基準すら無視する極めて不当なものであった。すなわち、退職強要は旧「判断指針」においても「心理的負荷の強度がⅢ」(人生の中で希に経験することもある強い心理的負荷)となっているのであるから、結論はさておき議論の出発点はここであるのに、大阪地裁判決は、完全にこれを無視して、「解雇によって受けた心理的負荷は、その程度が強いものであったとまでは認められない」としてしまったのである。
その結果、大阪地裁判決は、本件解雇の心理的負荷がたいしたことがないという前提で判断を押し進めていったため、必然的に「精神障害を発症するに値するほどの強い心理的負荷を受けた事実を認めることはできない」とし、仮に適応障害を発症していたとしても、本件解雇後の「脆弱性」などの個別事情に起因して発症したに過ぎないとした。
大阪地裁判決は、その脆弱性はアルコール依存症を否定する判断をしながらも、「アルコール依存傾向」があり、生活面での変調を認めて、被災者側の個別事情によって「精神的変調」をきてしていたとして、自殺企図の原因を被災者の「脆弱性」「個別事情」にもとめて業務起因性を否定してしまった。
(3) 大阪地裁判決の事実認定は概ね原告が立証したとおりであったこと
(基礎となる事実認定は概ね適切であったこと)
原告が主張立証した事実関係を概ね認定していたので、大阪地裁判決の誤りはその事実評価を誤ったことにあった。
弁護団としては、勝訴を期待していただけに敗訴判決には納得できなかったが、大阪地裁判決の事実認定をもとにして控訴審において逆転を狙うことができると確信していた。つまり、控訴審において事実の見方(評価)を変えさせることに成功すれば、大阪地裁判決は必然的に取り消されることになる。
第5 控訴審(大阪高裁)における訴訟活動
(1) 控訴理由書で勝負が決まる
当職のこれまでの経験や高裁裁判官の協議会における発言や「民事訴訟における事実認定」(法曹会)の中での高裁判事へのインタビューなどから、多数の事件を抱える民事の高裁の裁判官は、控訴理由書がまず期限内に説得的で原判決が誤りかも知れないと思わせることに成功して初めて、原判決と控訴理由書と書証を照らし合わせて原判決の見直しの可能性があるかどうかを真剣に考えてくれるはずと信じた(逆に弁護団の控訴理由書で裁判官にそのような感覚を植え付けることができなければ、原判決どおりで一回結審で原判決のとおりの控訴審判決が下されることになる。)。
精神論めいているが、弁護団の至上命題として、必ず説得的な控訴理由書を50日以内に提出して控訴審の裁判官に気合いをみせることが重要と考えた。
(2) 総合評価に持ち込む
労災事件で敗訴する場合、判決の判断の方法として各事実を個別に判断してそれぞれの事実は全体と切り離してみたらたいしたことがないというものが多い。今回の地裁判決もそのようなものであった。したがって、控訴審においては、総合的に事実を評価させることに留意した。
例えば、本件解雇は出来事として突然の面があったことは事実であるが、背景的な事情として、正義感の強い被災者が、会社において、他の同僚が金銭の横領をしていたことについて会社のためにその不正を糺すべきことを忠告したのに逆に犯人扱いされたり、そのような一連の流れで本件解雇に至っていること、大阪地裁判決が本件解雇後に再就職活動をしたり労基署に相談をしているという一見合理的な行動をしつつも、原判決が全く無視しているおかしな行動(一睡もせずに布団に座ってぶつぶつ言う、5月何に暑い暑いといいながら、冷房を入れたり、逆に寒い寒いといいながら毛布をかぶったりなどなど)を指摘しつつ、本件解雇の心理的負荷の高さを評価する際にも、発症の有無を判断する際にも事実を総合的に評価すべきことをもう一度証拠や証言等に基づいて事実を摘示しつつ示すようにした。
(3) 常に結審の可能性を意識して国に対する反論などは期日をのばさずに必ずやりきる
控訴審は常に結審の危険があるので、国から準備書面や書証が提出されたら、期日までの間隔が数日であっても、反論の準備書面や必要な書証を期日までに提出するようにした。
画期的な電通最高判決(過労自殺の企業責任を追及した初めての裁判)を生み出した故藤本正弁護士がたった1人でも実践し勝ち抜いた方法である。弁護団がこのようなことをやり続け攻め続けることによって、裁判官に控訴審の主導権が控訴人側にあるということを示そうとした。
(4) 大阪高裁が結論を見直そうとしている徴表(積極的な釈明)
被控訴人である国は、答弁書において「適応障害の症状は、その症状が直後・数日以内に顕在化するような疾患ではない」として、ICD-10の診断基準に真っ向から反する主張を行っていた。おそらく、国は発症を否定しようとする余り、外傷後ストレス障害(PTSD)の診断基準(外傷後、数週から数ヶ月にわたる潜伏期間を経て発症する)と混同して、国自ら根拠とするICD-10の診断基準に反する主張をしてしまっていた。当然ながら、弁護団は「ICD-10のガイドラインにおける適応障害の項目において『発症は通常ストレスの多い出来事、あるいは生活の変化の発生から1か月以内であり、症状の持続は遷延性抑うつ反応の場合を除いて通常6か月をこえない』とあり、出来事(本件では本件解雇がこれに該当)発生から1か月以内に適応障害を発症することが記載されているのであって、直後や数日以内に症状が出たり適応障害が発症することを否定するどころか、1ヶ月以内であれば、それは適応障害という前提の記載となっている。被控訴人のように出来事の「直後・数日以内に症状が顕在化しない」ということは、ICD-10のガイドラインの記載からは全く読み取れないどころか、積極的にICD-10のガイドラインに反するものである。出来事の直後や数日以内というのは1か月以内に該当するのであるから、むしろ、適応障害の症状の出る時期に該当するのである」などと反論していた。
しかも、裁判所が国に対し、国の上記主張がICD-10とほぼ同一内容の操作的診断基準であるDSM-Ⅳ-TRにおける記載と齟齬があることを証拠を指摘しながら、国の主張に医学的根拠があるのかどうかについて積極的に釈明を求めた。
裁判所がこのような求釈明を行うことは、発症の有無について原判決の判断に疑問を持っていることと記録をよく読んで検討してくれていることを意味しているため、原判決を見直す蓋然性が高まったと判断した。
(5) 結審時には全ての主張立証を尽くしたと断言できた
審理は平成24年4月26日に終了したが、その際に弁護団は裁判所から他に主張立証すべき点はあるかどうかとの問いかけに対して、全くないと自信を持って回答できた。
判決言い渡し日は平成24年7月5日で約2か月後であった。一般的に原判決を見直すにしては短いとの意見もあろうが、少なくとも当職はそのようなことは全く気にならなかった。確かに事実認定を根本的に変えて原判決を見直す場合にはそうかもしれないが、原判決の事実認定を基にその評価を変えて原判決を見直すのであれば、2か月もあれば必要にして十分であり、実際、大阪高判平成20年12月18日判決(判例タイムズ1334号91頁・和歌山地公災・福祉課係長橋出血死事件)で一審敗訴であったが、2回の審理で結審し逆転勝訴判決を獲得した際も、事実認定はほぼ原判決を踏襲してその事実の評価を変えてのもので結審後2か月程度で判決の言い渡しであった。
今回の裁判の結審時と福祉課係長橋出血死事件の控訴審における結審時との感覚は驚くほど似ていて、いずれも結審時にはやり尽くしたという点では悔いなくすがすがしい気分で後は天命(判決)を待つという心境であった。
第6 大阪高裁判決の概要
大阪高裁判決は、大阪地裁の事実認定をほぼ踏襲しながら、本件解雇の評価など適正にしたため、大阪地裁判決と正反対の結論となった。大阪高裁の逆転判決は一貫して被災者側が主張立証し続けたことを認めたものである。
(1) 本件解雇の心理的負荷を適正に評価
大阪高裁判決は、本件解雇は、「退職を強要された」という具体的出来事に該当し、「その心理的負荷の強度は、最高値の「Ⅲ」【人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷】」であるという判断指針の立場から出発しており、極めて妥当である。そのうえで判断指針の「心理的負荷の強度を修正する視点」の要素、つまり、「解雇又は退職強要の経過等、強要の程度、代償措置の内容等」に照らしてⅢから下げる修正の余地があるかどうかを検討している。大阪高裁判決は「本件解雇は控訴人にとって予期しない突然の出来事であり、社長と口論となるなど尋常でない経過があったことを考慮すると、上記Ⅲの評価を修正すべきであるとは言えず、業務による心理的負荷の強度の総合評価としては、「客観的に精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷といえる『強』にあたる」とした。
大阪地裁(被控訴人の主張でもある)が「辞めてやるわい」等と対応していたことなどから心理的負荷がさほどではないとの判断に対しては、同僚の非違行為について会社が「何らの処分もしないことに不満を高じさせていたところ、たまたま本件会社を訪ねてきた謹慎中の同僚を社用車に乗せて会話したというだけで、社長から突然本件退職通告を受けたことから、それまでの鬱憤が一挙に爆発し、上記のような応答となったもので、納得ずくで本件解雇を受け入れたものではない」として、表面的な応答の内容で表面的な判断に終始した大阪地裁判決を完全に否定する内容になっている。
そして、大阪地裁判決が事実認定しながら判断に際して無視していた通常でない身体の状態(食事を取らない、暑いと言ったり寒いと言ったり)をきちんと評価して、たとえ労基署に訪問するなど合理的な行動を取っているように見えてもそれが本件解雇による心理的負荷が強くなかったことを示すものではないとした。
(2) アルコール依存の否定
アルコール依存症の診断基準や知見に沿って、アルコール依存症を否定し、アルコール依存症又はアルコール依存傾向によって抑うつ症状などの精神障害を発症して自殺企図に及んだとは言えないとした。
(3) 大阪高裁判決の意義
退職強要という出来事を行政基準に従って適正に評価したこと、精神障害発症後でも一見合理的な行動を取ることがあること、それが精神障害を否定したり出来事の心理的負荷の強度が弱いものを示すものではないこと、精神障害発症と脆弱性とを安直に結び付けるべきでないことを明言している点で、意義がある。
第7 さいごに
10年近く介護をしつつ戦い続けたご家族のご苦労は並大抵のものではなく、その奮闘には頭が下がる思いであった。ここまで負けが続くと、愚痴や不満を述べられても当然であるが、ご家族は全くそのようなことを口に出されることもなく(それ故弁護団は何とか結果で報いたいと思いから重圧を感じてはいた。)、弁護団を信じて最後まで戦い抜いてくれた。
大阪地裁判決の敗訴判決後は訴訟継続を断念することを表明するところまで追い詰められていた(弁護団を気遣う気持ちも多分にあったようである)。しかし、当初からの弁護団である渡辺和恵弁護士と下川和男弁護士も10年近く関わり(途中から加わった当職でも4年以上)、弁護団としても、このまま終わることができず、相当強く控訴することを促していただけに、控訴審で逆転できて本当によかった。
以上
【弁護団:渡辺和恵弁護士・下川和男弁護士・弁護士波多野進【当職】】
当職(波多野)は民事訴訟の控訴審と労災の審査請求から弁護団に加わる。